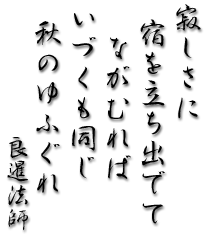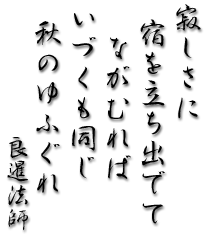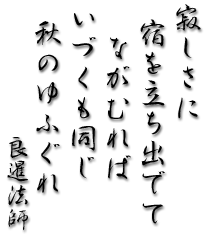

|作り方|
今回のお菓子は、「宿を立ち出て」というところから「宿」を中心にイメージして作りました。この歌から、秋の夕暮れにたたずむ山里の「合掌造りの茅ぶき屋根」を思いました。
「合掌造り」と言えば岐阜県 飛騨 白川郷の合掌造りの集落が有名です。1995年12月にユネスコの世界文化遺産に登録されました。なぜ、登録されたのかそのわけは、文化や伝統、歴史もさることながら1番の理由は「結(ゆい)」だそうです。
合掌造りはおよそ80年に1回、屋根の茅を取り替える(屋根ふき)をしなければなりません。これにはたくさんの人手が必要です。村の人達はもちろん、隣村の人、中高校生をはじめ、全国から300〜400人の人達が無償で茅を替えるその日1日だけに集まります。(業者に頼むと3000万円くらいするそうです。)この集まりを「結(ゆい)」といいます。女性は、お茶や食事でもてなします。助け合いによる「屋根ふき」。人と人とのつながり。助け合いを当然のことと思う村
の人達。村がひとつになり、絆を確かめ合う「結の心」。村の人達は「茅ぶき屋根は、自分のものであり、みんなのもの」だといいます。IT化が進む近年、人と人を結ぶコミュニケーションが大切だと思います。
練切生地で、合掌造りの家を写実的に表現しました。小豆練切を張り合わせ、「茅ぶき屋根」をイメージしました。練切生地を手で形作るときのポイントは、素早く仕上げることです。手の熱が生地に伝わって乾燥しやすく、いたみが早くなるからです。
今成 宏

|