|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
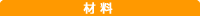 |
 |
 |
 |
| 約30個分 |
 |
| 薯蕷生地 |
 |
|


 |
 |
|
山の芋 |
|
 |
60g |


 |
 |
|
上白糖 |
|
 |
120g |


 |
 |
|
上用粉 |
|
 |
72g |


 |
| 中餡 |
 |
|


 |
 |
|
小豆こし餡 |
|
 |
300g |


 |
| 薯蕷練切生地 |
 |
|


 |
 |
|
山の芋 |
|
 |
400g |


 |
 |
|
上白糖 |
|
 |
200g |


 |
 |
|
白こし餡 |
|
 |
300g |


 |
| 錦玉羹 |
 |
|


 |
 |
|
糸寒天 |
|
 |
4g |


 |
 |
|
水 |
|
 |
300ml |


 |
 |
|
グラニュー糖 |
|
 |
180g |


 |
 |
|
水あめ |
|
 |
20g |


 |
| 副材料 |
 |
|


 |
 |
|
食用色素 (水紅色) |
|
 |
少量 |


 |
 |
|
食用色素 (本紅色) |
|
 |
少量 |


 |
 |
|
食用色素 (黄色) |
|
 |
少量 |


 |
 |
|
食用色素 (水色) |
|
 |
少量 |


 |
 |
|
食用色素 (草色) |
|
 |
少量 |


 |
 |
|
銀ぱく |
|
 |
適量 |


 |
| 酢 |
 |
少量 |


 |
 |
|
 |
 |
 |
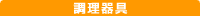 |
 |
 |
 |
| ボウル |
 |
|


 |
| せいろ |
 |
|


 |
| さらし |
 |
|


 |
| 蒸し器 |
 |
|


 |
| クッキングペーパー |
 |
|


 |
| 霧吹き |
 |
|


 |
| 小田巻き |
 |
|


 |
| そぼろごし |
 |
|


 |
| きんとん箸 |
 |
|


 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
薯蕷生地を作る
 |

 |
 |
| 1. |
すりおろした山の芋と上白糖を混ぜ合わせ、水紅色の食用色素で着色する。
 |
|
 |
|

 |
 |
| 4. |
芋のかたまりの片側を持ち、外側から内側に折りたたみながら、まわりについた粉を少量づつ混ぜ込む。
 |
|

上用粉を一度に多く混ぜてしまうと、きめが粗くなり、浮きが悪くなります。
 |
|

 |
 |
| 5. |
生地が耳たぶくらいのかたさになるまで、内側に折りたたむ作業をくり返す。
 |
|
包餡する
 |

 |
 |
| 6. |
小豆こし餡を10gずつ、薯蕷生地を8gずつにそれぞれ分割し、包餡する。
 |
|
 |
|
包餡の仕方
 |
|

 |
 |
| 7. |
せいろに、ぬらしてかたく絞ったさらしとクッキングペーパーを敷き、酢を少量加えた霧を吹き、10分蒸す。
 |
|

少量の酢を加えた霧を吹きつけておくと、表面につやが出ると同時に、蒸したときに亀裂も入りにくくなります。
 |
|
薯蕷練切生地を作る
 |

 |
 |
| 8. |
これが「小田巻き」。筒の先に口金をつけ、生地を入れ、押し棒で押し出し糸状にする器具。
 |
|

口金は丸い板金で、丸穴には大小あります。2穴から16穴まであり、使用目的によって取り変えることができます。
 |
|

 |
 |
| 9. |
薯蕷練切生地のうち1/3を小田巻きで押し出すために取り分ける。このうち、1/2を水紅色の食用色素で着色する。水紅色の生地と着色していない白生地を重ねて平たくし、真ん中でちぎり、片方の上にもう一方を重ねる。手の平で生地を少し平らにし、真ん中でちぎって上下に重ねる。このようにしてマーブル模様にする。
 |
|
薯蕷練切
 |
|

 |
 |
| 10. |
生地を転がして棒状にし、小田巻きの筒へ生地を入れる。
 |
|

今回の口金は4穴を使用します。
 |
|

 |
 |
| 12. |
残りの薯蕷練切生地を、半分に分ける。一方を5等分し、草色、黄色、水色、水紅色、オレンジ色に染め分ける。白生地も5等分にする。染めた生地と白生地を組み合わせ、それぞれ白生地を上にしてそぼろごし器でこしてそぼろにする。
 |
|

白生地を上にしてこすと、淡い上品な色合いになります。
 |
|

 |
 |
| 13. |
配色のバランスを見ながら、12のそぼろをつける。
 |
|

カップを台にしてつけると、下の方のそぼろがつぶれません。
 |
|
仕上げ
 |

 |
 |
| 14. |
錦玉羹を作り、紙のコルネに入れ、クッキングペーパーの上に絞り出し、固める。
 |
|
錦玉羹
 |
|
 |
 |
 |
| | |
