|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
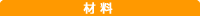 |
 |
 |
 |
| 60個分 |
 |
| 小豆羊羹 |
 |
|


 |
 |
|
糸寒天 |
|
 |
4g |


 |
 |
|
グラニュー糖 |
|
 |
150g |


 |
 |
|
小豆こし餡 |
|
 |
330g |


 |
 |
|
水あめ |
|
 |
20g |


 |
| 味甚羹(小豆こし餡入り) |
 |
|


 |
 |
|
糸寒天 |
|
 |
12g |


 |
 |
|
水 |
|
 |
850ml |


 |
 |
|
グラニュー糖 |
|
 |
560g |


 |
 |
|
小豆こし餡 |
|
 |
160g |


 |
 |
|
水あめ |
|
 |
60g |


 |
 |
|
上白糖 |
|
 |
48g |


 |
 |
|
味甚粉 |
|
 |
48g |


 |
| 錦玉羹 |
 |
|


 |
 |
|
糸寒天 |
|
 |
7.5g |


 |
 |
|
水 |
|
 |
550ml |


 |
 |
|
グラニュー糖 |
|
 |
350g |


 |
 |
|
水あめ |
|
 |
30g |


 |
| 小豆こし餡(中餡用) |
 |
600g |


 |
 |
|
 |
 |
 |
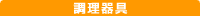 |
 |
 |
 |
| 鍋 |
 |
|


 |
| 木杓子 |
 |
|


 |
| さらし |
 |
|


 |
| ボウル |
 |
|


 |
| 泡立て器 |
 |
|


 |
| レードル |
 |
|


 |
| 流し缶 |
 |
|


 |
| まな板 |
 |
|


 |
| 包丁 |
 |
|


 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
中餡の準備
 |

 |
 |
| 1. |
中餡にする小豆こし餡を1個10gずつの餡玉に分ける。餡玉のまわりに、小豆蜜漬けをまぶす。
 |
|
小豆こし餡
 |
|
小豆の蜜漬け
 |
|

 |
 |
| 2. |
小豆の蜜漬けを手に取り、上に餡玉をおき、まわりに小豆の蜜漬けをすき間なくつける。
 |
|

 |
 |
| 4. |
木杓子の上におき、上から錦玉羹をかける。
 |
|

錦玉羹は少しあら熱を取っておきます。熱いままかけると、すぐに流れてしまい、つやが出ません。
 |
|
錦玉羹
 |
|
こし餡入りの味甚羹を作る
 |

 |
 |
| 9. |
水あめを加え、木杓子で全体を混ぜて煮溶かし、火を止める。
 |
|

 |
 |
| 10. |
上白糖、味甚粉をボウルに入れ、泡立て器で均一に混ぜ合わせる。
 |
|

 |
 |
| 12. |
さらに少しずつ加え、混ぜ合わせる。
 |
|

ダマができないようにしっかり混ぜる。
 |
|

 |
 |
| 13. |
分離を防ぐため、ボウルごと冷水にたあて、あら熱を取る。
 |
|

味甚粉が軽いため、二層に分かれやすいです。分離を防ぐために冷水であら熱を取り、味甚羹に濃度をつけます。ただし、味甚羹を冷やしすぎると固まってしまうので、注意しましょう。
 |
|
練羊羹を作り、味甚羹を流す
 |

 |
 |
| 14. |
流し缶1枚にえ5mmの厚さ(約160g)になるように、小豆羊羹を流す。
 |
|
小豆羊羹
 |
|

 |
 |
| 15. |
半どまりの状態を確認する。
 |
|

半どまりの状態とは、ぬらした指先で押し、指先に生地がつかず、柔らかい状態のことです。
 |
|

 |
 |
| 16. |
半どまりの状態に合わせて、味甚羹を流す。
 |
|

流し合わせの場合、先に流した生地が完全に固まってしまうと、次の生地を流しても、はずれてしまいます。半どまりのタイミングを見のがさないようにしましょう。
 |
|

 |
 |
| 17. |
流し缶の縁より約1cm下まで流し、冷やし固める。
 |
|

 |
 |
| 18. |
流し缶と生地の間に一文字へベラをさし込み、すき間を作る。
 |
|

 |
 |
| 19. |
流し缶12cmの面にヘラをさし込み、少し引っかけるように手前に引き出す。
 |
|

あまり強く引っかけると、生地に傷をつけてしまうので気をつけましょう。
 |
|

 |
 |
| 20. |
12cmの面を縦にして、3mmの厚に包丁で切る。
 |
|
仕上げる
 |
 |
 |
 |
| | |
