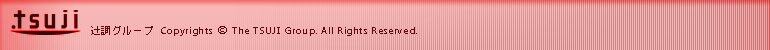|
|
 |
 |
 |
 |
 |
「地方料理の集合体」などと形容されるイタリア料理。ちょっと堅苦し〜い表現ですが、つまりは「土地のマンマ(お母さん)の味」ということ。「イタリアの家庭で作られるおふくろの味を日本の食卓へ!」をテーマに、皆さんよ〜くご存知のこれぞイタリア料理から、日本では無名に近い地方料理まで、ただひたすら個人の趣味でご紹介。「イタリア料理はmammaのマンマ」の思いをタイトルに込め、辻調グループ校「イタリア大好き!!!」職員が、遠き恋しきイタリアを想いながら好き放題、いえ、自由に綴る偏重コラム。星付きレストランの料理も!と、時にはテーマを外れて大暴走なんてことにも!? |
 |
|
 |
 |
|